事例で解説!BCP対策(事業継続対策)とは?

企業の予期せぬトラブルや災害の際に、業務の円滑な遂行を継続させるためのBCP対策。地震リスクのある日本では、このBCP対策は欠かせない要素であり、人的な安全性や企業資産の保護を目的としています。
BCP対策とは
BCP対策とは企業が、地震、津波、大雨、大雪などの自然災害や事故、停電など、予測不可能な緊急事態に見舞われた際に取るための施策で、重要業務の被害を最小限に抑え、企業運営を滞らせないための行動指針です。トラブルによる業務の停滞は、顧客流出や企業の信頼を損なう恐れもあり、BCP対策によるリスクヘッジは企業にとって必要不可欠な取り組みとなっています。
BCP対策の意味は広く、緊急事態時に迅速に行動できる対策チームの設立や避難訓練などの人的対策から、インフラの確保、企業資源の確保なども含まれます。
「分散化」はBCP対策の第一歩
 BCP対策の代表的な例として、「分散化」が挙げられます。
BCP対策の代表的な例として、「分散化」が挙げられます。
分散化は、災害時やトラブルの際に地域やインフラの影響を排除するため、業務の拠点や基幹システムを複数の地域に分散させる方法です。一部の地域で災害やトラブルに見舞われても、社内システムや在庫などの資源が他の拠点から確保でき、業務を停止させることなく企業活動を継続できた、という事例があります。
しかし、この分散化には基幹システムや分散場所の確保など、通常時でもランニングコストがかかり、トラブルや災害は発生地域・時間が予測できず、分散先の選定が難しいというデメリットもあります。
「代替手段」について
BCP対策のひとつである分散化のコストデメリットを解消するのが「代替手段」と呼ばれる方法です。
この代替手段は、トラブルや災害が発生した際に事業の継続性を守るため、重要なインフラやシステム、体系を一時的に別の方法で代替する手段です。急な停電で業務がストップしてしまわないために自家発電装置を用意しておくことで企業活動を継続できた事例があります。このように、もともとのインフラやシステムをいくつも持つのではなく、一時的なトラブルに対応できる手段を用意しておくことで、不測の事態でも業務を継続させることができます。 この代替手段では、代替設備の初期投資がかかりますが、分散化にかかる二重コストを抑えることができます。
通信インフラを守る転送電話
 転送電話は、有効的な代替手段のひとつです。 通常の電話は、緊急時につながりにくくなります。
これは、各通信キャリアが緊急電話の通信を守るため、一般の通信回線には制限をかけるためです。
また、災害などによって基地局が機能しなくなった場合、基地局が復旧するまでその地域での電話は使えなくなってしまいます。
このような通信インフラのリスクヘッジのひとつとして、転送電話が活躍します。
転送電話は、有効的な代替手段のひとつです。 通常の電話は、緊急時につながりにくくなります。
これは、各通信キャリアが緊急電話の通信を守るため、一般の通信回線には制限をかけるためです。
また、災害などによって基地局が機能しなくなった場合、基地局が復旧するまでその地域での電話は使えなくなってしまいます。
このような通信インフラのリスクヘッジのひとつとして、転送電話が活躍します。
インターネット回線を使うため、転送電話は通常の電話と通信網が異なります。 そのため、一般的な電話のような通信規制がかかることがありません。 実際に東日本大震災の際には、通常の電話がつながらない中で、Skypeなどのインターネット回線を用いた電話は使用できたという事例もあります。 加えて転送電話は、電話をしている両者の距離に関係ない料金が設定されているため、通常の電話に比べて毎月の通信料金を安価に抑えることができます。
他に、災害時などにシステムから送信されるアラートメールを受信して、担当者に電話で知らせる方法もあります。 メール通知だけでは大量に届く他のメールに埋もれてしまい、対応が後手に回ってしまう可能性がありますが、転送電話での通知なら、迅速かつ確実に業務の担当者に連絡できます。転送電話はインターネット回線を使用しているため安価です。
メールをトリガーとして電話発信する仕組みを活用するのも、業務継続に非常に有効な手段です。
おわりに
地震リスクのある日本において、企業のBCP対策は必要不可欠となっています。企業の規模によって取ることができる対策の大小は変わりますが、大切なのは緊急事態が起きた際の心構えと、迅速かつ最適な対応を取るための仕組み作りです。
BCP対策とは、決まった機器を導入することではなく、いざという時に事業を継続させるための手段をあらかじめ用意して、不測の事態に対応できるよう、組織を整えておくことが大切です。

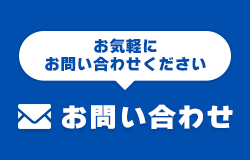
 「転送録」を試してみる
「転送録」を試してみる

 お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら